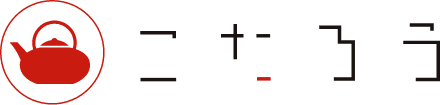赤絵と色絵/宋赤絵・柿右衛門・藤本能道・色絵磁器・釉描加彩

●下絵と上絵
陶器を華やかにする絵付け。益子や笠間、有田、九谷といった窯業地で観光客に簡単に楽しんでもらうために、絵付け体験をさせてもらえる窯元は多い。この絵付け体験ではほとんどが下絵という釉掛けする前に行う絵付けがほとんどである。ただし九谷焼の地元・石川県では、白い磁器に上絵付けをさせてもらえるところもある。この上絵の場合は、すでに一旦完成された磁器に、さらに釉掛けすることなく、そのまま低温で焼成して絵の具を定着させている。上絵の具での絵付けは絵の具の濃度と絵の具の置き方にコツが必要なので、下絵付けよりは難しくなる。
一般的には、上絵付の方は色彩がはっきりしており、絵の完成度は高いように思われる。釉薬の下にした絵の具で彩色した場合、釉薬をかけて焼成すると、どうしてもぼやけた雰囲気となってしまう。ただし、下絵の具のメリットとしては焼成前と焼成後の色の変化が少ないことにある。明治時代に下絵の具の研究が進み、ほぼ書かれた絵がそのままの色合いで焼き上がり、思い通りの発色が得られるようになった。そのメリットを生かして下絵作品を製作したのは、板谷波山や真葛香山であった。
●上絵の具の発展
中国では元の時代には五彩という上絵の具の使用した陶器が作られた。つまり13世紀にはすでに上絵の具が完成し、明時代には色絵磁器として発展・完成していった。その上絵の具を使用した技法が日本に渡来したのは江戸時代である。真偽は定かではないが、ここで登場するのが初代柿右衛門こと酒井田喜三右衛門である。昭和前半までの小学校の教科書で紹介され、歌舞伎でも演じられていたように、庭になった柿の実の赤を焼き物にできないかと苦心する陶工の物語である。この赤絵の具の技法を習得した柿右衛門が日本では色絵磁器の創始者であるとされていた。
日本の陶磁器に使用される色絵の具は、先の赤を除いて焼成前と焼成された後の発色が異なる。したがって、色の調整はテストピースを焼成し、幾度となく調合を試みなければならない。ただし19世紀から20世紀に完成された西洋絵の具では和絵の具とは、組成が大きく異なり、焼成前後での色の変化は少ない。概ね油絵の具に近い感覚で取り扱える。
●下絵の具と上絵の具の組合せ
有田焼で染錦とよばれている技法がある。これは下絵の具として青い呉須で描いていったん焼成し、さらに上絵の具で彩色するという技法である。いわゆる「色鍋島/染錦」と呼ばれており、江戸自体から佐賀の鍋島藩の専売特許の技法であり、現在まで続く今泉今右衛門窯がその代表である。呉須のメリットである濃淡の表現を使えば、より味わいある絵が出来上がる。一方、同じ有田焼でも酒井田柿右衛門窯は、染錦の技法も使用するが、本焼き後の純白の素地の上に直接、上絵を描いて完成させる技法に長けていた。柿右衛門窯では、輪郭線や模様の線は呉須を用いている。この場合、呉須は本焼き後の素地の上では再度焼成しても定着しないので、その上に色絵の具をかぶせてから焼成している。これは「没骨技法」と呼ばれる。有田焼や九谷焼で伝統的な色絵に取り組む窯元では、現在もこの技法が基本である。

●色絵の革新・藤本能道「釉描加彩」
後に人間国宝に指定される陶芸家・藤本能道は二つの色絵の革新に取り組んだ。一つは先の没骨技法の応用である。藤本は輪郭線での呉須の利用のみならず、墨絵のようにぼかして面で使用することにより、その上に乗せた色絵の具に濃淡を与えた。たとえば、木の肌の凹凸や光の加減を表現することに成功している。
もう一つは「釉描加彩」である。釉描とは、釉薬を掛けた後に絵の具で彩色するで素地に色を付けることである。加彩とは概ね上絵付と思ってよい。この技法によって可能となったことは、白い素地でしかない余白を背景として使用し、器全体を絵付作品にすることを可能とした。釉描自体は藤本以前にも行われていたことであるが、藤本は釉描の安定性を求めて、素地となる釉薬の開発も独自に行っている。こうして和絵の具の伝統をベースとした色絵作品は藤本の技法によって高い絵画性を持つものとして完成された。