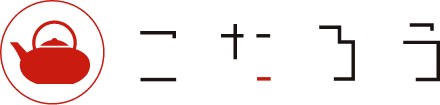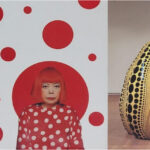掛け軸の基礎知識|価値ある掛け軸の特徴・有名作家一覧

現代において、新作日本画では掛け軸という装幀をされることが極めて少なくなってしまいました。書の作品では、未だ掛け軸は主流ではありますが、額装される作品が増えており、日本画と合わせても、掛け軸という装幀は「絶滅危惧種」ともいえる存在になりつつあります。とはいうものの、古来からの書画は掛け軸で装幀された作品は多数存在ますので、日本や中国の作品の中で残されている掛け軸の数は膨大なものとなっています。
今回は、掛け軸の基礎知識を整理するとともに、価値のある掛け軸についてご案内いたします。
掛け軸の基礎知識
掛け軸は、今でも美術館やギャラリーでの出品作品で見ることがありますが、日常生活では目にすることが少なくなってしまいました。昭和以前の日本画では、掛け軸の作品が多く、特に縦長の構図を生かした日本画は、掛軸ならではの世界といえます。
はじめに、掛け軸の構造や歴史を振り返ります。
●掛け軸の概要
掛け軸とは、本画である書(文字)や絵(絵画)紙や布で裏打ちして補強し、装飾をほどこして、その上下に竹木などの軸を付け、床の間などで飾れるように仕立てたものです。こうした、書や絵などの書画を掛け軸などに仕立てることを表装といいます。縦長の掛け軸は「縦軸(たてじく)」や「条幅(じょうふく)」、横長の掛け軸は「横福(よこふく)」と呼ばれることがあります。
●掛軸の由来と歴史
飛鳥時代に仏教が中国から日本へ伝来したとともに、掛け軸が日本へ伝わったと言われています。中国において掛け軸には仏様が描かれており、仏教の礼拝の対象だったものです。時代の経過とともに掛け軸をかける目的や種類が多様化しました。平安時代には貴族や公家たちが掛け軸を愛好するようになり、以後、掛け軸は伝統的な美術品として地位を確立しました。室町時代には、茶道の発展により、茶会の雰囲気を演出する用途で使われるうになりました。これが「茶掛」という茶道具の一ジャンルとなります。
●現代の掛け軸の用途
現代において掛け軸は主に「床かけ用」と「仏壇用」の2つの用途があります。
床かけ用は部屋を彩る装飾品として、以前から親しまれてきましたが、昨今の住宅事情により床の間自体を持たない家屋が増えていることはご承知のことと思います。
季節の花や鳥、景色を描いた掛け軸や縁起物の掛軸など、さまざまな種類がありました。一方の仏具用の掛け軸は仏壇にかける用途で使われているもので、昨今ではスタンドを使用してかけることが多くなりました。
価値ある掛け軸の特徴
新しい掛け軸は少なくなってきた昨今ですが、それでは今残されている掛け軸にはどのような価値があるのでしょうか?
以下では、価値がある掛け軸についてご紹介いたします。
●有名作家の掛け軸
有名作家の掛け軸は高額な傾向にあります。作家の落款や銘(サイン)の有無で、有名作家の掛け軸か確認する方法があります。
落款(らっかん)とは、書画の作成時に作家が記名などを示すために施した署名や印であり、絵画の隅や保管されている木箱に記されています。
ただし、この落款は悪意ある偽作者によって画家本人作以外の作品に書くことがあり、真作かどうかは慎重に調べる必要があります。
また、木箱の落款が画家本人以外であるものも多く存在しており、その場合、本人の落款がある木箱(共箱)でないと、価値が下がってしまいます。
●希少性が高い掛け軸
出回っている数が少ない掛け軸は、価値が高いとされています。一つは制作年代が古い掛け軸です。掛け軸は劣化しやすく、日本国内では天災や戦禍により失われるてきたため、古い年代の掛け軸は希少な傾向にあるといえます。もう一つとして、寡作の作家が存在します。著名な画家では、菱田春草(36歳没)、速水御舟(40歳没)などは早世のため作品数がかなり少ない日本画家です。
●保存状態が良い掛け軸
制作時の状態が維持されている、保存状態が良い掛け軸ほど、高値になる傾向があります。日焼けによる色あせや虫食い、湿気によりカビは生えているなどの劣化があると価値が低下がりやすくなります。また、掛け軸は作品そのものの紙と表具自体の相性により、長時間の保管により折れが自然と生じてしまうケースがあります。
こうした、劣化した掛け軸は表装をやりなおすことで、その価値をある程度取り戻すことができます。
掛け軸の有名作家一覧
では、日本の掛け軸作品で有名な巨匠を以下でご紹介しておきます。
●特に価値が高いとされている有名な掛け軸作家(あいうえお順)
・伊藤 若冲(いとう じゃくちゅう/1716年~1800年)
江戸時代に京都で活躍した画家です。当初は狩野派に学んだとされていますが、独自の画法へと突き進みます。2000年に京都国立博物館で若冲の没200年を記念した展示をきっかけに再注目され、現在も国内外で人気がある画家です。
代表作:「動植綵絵(どうしょくさいえ)」は「釈迦三尊像」を荘厳するために描かれた、30幅に及ぶ花鳥図の大作。
作風:植物,鳥,昆虫などが生き生きと鮮やかに描かれている作品を多く目にします。特に、鶏は実際に数十羽を飼っており、日々その姿を何年も観察していたとわれており、最も定評のあるモチーフです。その他、山水画なども手掛けています。
・上村 松園(うえむら しょうえん/1875年〜1949年)
明治から昭和にかけて活躍した女性日本画家で、女性初の文化勲章の受章者です。美人画を得意としており、伝統的な日本画の技法を基盤としながらも、独自の美意識と女性ならではの視点で描かれた作品で人気があります。文展で作品は発表されていました。
代表作:『序の舞』(重要文化財指定)、『母子』、『花がたみ』など
作風:伝統的な日本画の美しさと、女性ならではの視点が融合した独特の魅力を持っており、その清澄で気品ある美人画は、今なお多くの人々に愛されています。
・榊原 紫峰(さかきばら しほう/1887年〜1971年)
明治から昭和にかけて活躍した日本画家です。伝統的な技法を踏まえつつも独自の表現を追求した点で高く評価されています。また、美術学校で後進の指導にもあたりました。
代表作:『青梅』『梅花群禽』など
作風:生涯を通じて小禽や花鳥画を中心に制作し、初期には鮮やかな色彩を用いた作品を描いていましたが、次第に清らかな透明感を持つ画風へと変化し、晩年には墨を主体とした静寂な作品を多く手掛けました。
・西村 五雲(にしむら ごうん/1877年〜1938年)
明治から昭和にかけて活躍した日本画家です。師事した竹内栖鳳の写実主義を受け継ぎながらも、五雲の作品はより繊細で観察力に基づいた描写が際立っています。特に動物画では、師である栖鳳を凌駕するとの評価を受けることもあります。帝展で作品は発表されていました。
代表作:『咆哮』『曲馬』など
作風:伝統的な日本画の技法を基盤にしつつ、西洋の写実主義や視覚的な奥行き感を取り入れました。細部へのこだわりが強く、毛並みや羽の質感を精密に描き、動物の持つ生命感を引き出しました。色彩表現は控えめでありながらも、自然な陰影やグラデーションを通じて対象の立体感を表現しています。墨の濃淡を巧みに使い分け、動物の存在感や躍動感を際立たせることに成功しています。
・円山応挙(まるやま おうきょ/1733年〜1795年)
江戸時代中期から後期にかけて活躍した日本画家です。水墨画においても写生を重視した「円山派」の創始者として知られています。
代表作:『雪松図屏風』『松に孔雀図』など
作風:自然の美しさを忠実に再現しつつ、独自の芸術的表現を追求した点で高く評価されています。また、革新的な技法や表現は、後の日本美術に多大な影響を与えと言われています。
・山口 華陽(やまぐち かよう/1899年〜1984年)
明治から昭和にかけて活躍した日本画家です。師である西村五雲や竹内栖鳳から円山・四条派の写生の伝統を受け継ぎつつ、近代西洋画の技法も取り入れ、新たな時代にふさわしい花鳥画を創出しました。
代表作:『黒豹』『駱駝』など
作風:生涯を通じて、写生中心の画風を貫き、動物画を得意としました。
●【時代別】有名な掛け軸作家
1.江戸時代
・谷 文晁(たに ぶんちょう)
2.江戸〜明治
・森 寛斎(もり かんさい)
・池上 秀畝(いけがみ しゅうほ)
・狩野 芳崖(かのう ほうがい)
・菱田 春草(ひしだ しゅんそう)
3..明治〜大正
・鈴木 松年(すずき しょうねん)
・富岡 鉄斎(とみおか てっさい)
・今尾 景年(いまお けいねん)
4.明治〜昭和
・竹内 栖鳳(たけうち せいほう)
・川合 玉堂(かわい ぎょくどう)
・川村 曼舟(かわむら まんしゅう)
・三輪 晁勢(みわ ちょうせい)
・山元 春挙(やまもと しゅんきょ)
・山本 倉丘(やまもと そうきゅう)
・前田 青邨(まえだ せいそん)
・横山 大観(よこやま たいかん)
5.大正〜昭和
・小林 古径(こばやし こけい)
その他、大和絵や文人画、南画などさまざまな掛け軸が残されています。
掛け軸を譲り受けたら、その価値を知ろう! 有名な作家の作品には思わぬ価値が!
以上でご案内した通り、かつて掛け軸には普段使いの作品が多くありました。一方、有名な市場価値がある作品では、現在のような額装がありませんでしたので、掛け軸として保管されていたのが一般的です。そのため、価値があるかどうかについては、まずは作家の作品かどうかの判断が手始めです。
もし、今回ご紹介した作家の作品がございましたら、ご売却をお考えの際に、掛け軸買取の実績ある骨董品買取こたろうまでお問い合わせください。
骨董品買取こたろうでは掛け軸作品のご売却・ご処分を承ります。
掛け軸作品のご処分なら、経験豊富なプロ査定士/鑑定士/専門家が在籍し、安心・便利で実績ある買取専門店・骨董品買取こたろうにお任せください。
価値不明でも掛け軸作品の鑑定から買取り価格の提案まで、親切丁寧に説明対応いたします。
作品を拝見し、詳細豊富な買取相場データから弊社査定員・スタッフが適正適切、満足いただける査定価格・買取価格をご算出提示します。お値段が納得できなければ、お断りいただいても大丈夫。また写真での査定もお手軽でおすすめです。
こたろう店舗での店頭買取や自宅への出張買取、宅配買取・郵送での買取方法に対応いたします。
全国出張料無料・手数料無料・無料査定で納得の高値買取の当店をご利用ください。ご都合が悪くなってもキャンセル料もなし。一切費用なし。掛け軸作品以外もご相談ください。
《買取品目の例》
絵画(西洋絵画・洋画、日本画、水墨画、油彩画・油絵、水彩画、木版画)、掛け軸・掛軸、屏風、色紙、現代美術・現代アート・現代アーティスト作品、西洋アンティーク・西洋美術、中国骨董・中国美術、陶磁器(瀬戸焼・備前焼・九谷焼)、ブロンズ彫刻・置物作品(ブロンズ、仏像)、ガラス工芸、鉄瓶・銀瓶、花籠 茶道具(茶碗・茶釜・香炉・花入/花瓶)、食器・漆器(蒔絵)、刀剣・刀装具、根付、象牙製品、翡翠、珊瑚、香木、切手・古銭、ビスクドール、工芸品・古美術品・骨董品の高価買取対応しています。
アンティーク家具、お酒、ブランド商品、宝飾品、貴金属、金製品・銀製品など買取などさまざまなお品物も買取実績が豊富な当店にご相談・お問合せください。
ご自分のコレクションのみならず、未額装の絵画、ご実家でご親族が購入し、倉庫に残ってあった多数・大量のお品物の査定やご処分、ご売却・現金化などにも対応可能です。
国内外の大手オークションへの出品もお気軽にご相談ください。
骨董品買取こたろう|確かな目利きで高額査定
URL: https://kotto-kotaro.com/contact/
WEBからメール、LINEで簡単査定! 24時間受付中!お気軽にどうぞ!