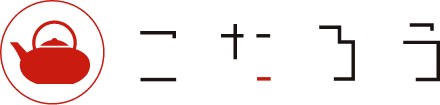雲破処

「雨過天晴雲破処」。それは中国の10世紀中期・後周の皇帝・柴栄の言葉から始まる。意味は、雨が過ぎ、雲間の天の青を持ち来たれ、という命令だ。それから、天青を作る中国人の戦いが始まる。澄んだ青色を持つ青磁づくりの始まりである。
10世紀以前にも、青磁と呼ばれる中国陶器はある。越州窯で焼成されていた緑がかったオリーブグリーンの青磁はすでにあった。原始的な青磁であり、古いながらも評価は下がる。
時は経て、12世紀に青磁らしい作品が生まれた。北宋後期の汝窯青磁である。古さもあるが、元々宮廷備品のため古美術品としていま目にできるものは極めて少なく、現在までに世界中で確認できた汝窯青磁の点数は60点ほどとされている。
2017年10月、香港サザビーズのオークション。直径13cmほどの青磁皿の落札された。価格が当時の日本円で42億円を超える額。これが汝窯青磁であった。同社で扱った東洋美術の落札額レコードである。
実はこれと同タイプの汝窯青磁が日本の博物館で常設展示として見ることができる。東京・上野にある東京国立博物館(美術愛好家は「トーハク」と呼ぶので、覚えておくと玄人っぽい?)・東洋館の展示品である。かつてはノーベル文学賞の受賞小説家・川端康成が所蔵していたというものであるが、42億円の汝窯青磁もトーハクの汝窯青磁もただの皿といえば皿である。手にできればいろいろいじくりながら見るであろうが、ガラス越しに見ているだけであれば、すぐ飽きて一分ももつまい。
編集子もいくつかの展覧会・台湾故宮博物院の図録などで汝窯青磁を見ているが、完成度としてまだまだの青磁だったと思われる。理由は二つ。よくみると、貫入が目立つ。貫入は使用に伴い、汚れがすすむ。もしかしたら、宮廷では汚れの増加と伴って、打ち捨てられたかもしれない。もう一つの理由は、色むらがあるものが多い。基本的に青磁の釉薬は厚く掛けないとしっかりした青とならないが、汝窯青磁はやや薄い。また、釉薬の成分の関係かムラムラとしたような曇りも感じる。しかし、これらの特徴を持つ青磁が汝窯青磁と判断されているのだから、アバタもエクボである。

13世紀になると、青磁のスタンダードとも呼べる完成度の高い青磁ができあがる。龍泉窯で「砧青磁」と日本で呼ばれる青磁が安定的に作られるようになった。まさに天晴の青。「砧」というのは、円柱の中心に棒が挿し込まれた木製のハンマーのようなもので、織られた布地を叩いてしわ伸ばしや艶を出す道具。かつて、中国から伝来した龍泉青磁の花入にあった「ヒビ割れ」を「ヒビキ/響」と転成し、砧を使用するときの叩く音に、茶人・千利休がこの意を重ねたことに由来するとされている。日本人が一番好む青磁が、無貫入で澄んだ青色の砧青磁であるといわれている。
同時期に中国では南宋官窯という窯で青磁が生産されるようになる。こちらの青磁は貫入が無数に入る青磁である。「亀甲貫入」という氷裂状の貫入であり、厚い釉薬の層の上下に貫入が入る「二重貫入」も見られる。さらに、この南宋官窯では「米色磁」という、黄色みがかった青磁も生産されている。こちらは、青磁の焼成技術で一般的な還元焼成という方法ではなく、酸化焼成とい方法によるものである。
かつて日本の陶芸家の間では「青磁をやると身を滅ぼす」と言われ、青磁への取組を忌み嫌う傾向があった。昔は窯業機材や材料、技術が確立されておらず、製品が安定しないため、製品ロスを考えると商売として成立が難しかったからだ。厚掛けられた釉薬はピンホールを起こしやすい。陶土への食いつきが弱いと釉薬が剥がれ落ちてしまう。還元焼成が的確に行われていないと、色ムラが生じる。特に、薪窯の時代は還元焼成のコントロールが難しかったはずだ。
編集子も時々、青磁を作る。現在では、釉薬の調合が概ね明らかになってきており、よい色の青磁は決して不可能ではない。基本的には、微量の鉄分を含み、細かな気泡ができるような釉薬の調合で得られる。しかし、ピンホール、溶けすぎて流れる、逆に溶けないで表面がカサつく、など完品を得る難しさは今でも変わらない。それが青磁である。
関連記事
買取実績
こたろうの買取品目一覧
絵画
掛軸
茶道具
陶器・磁器
中国骨董品
刀剣・日本刀・武具
工芸品
漆器
彫刻
木工品
西洋アンティーク・西洋陶器・西洋美術品
珊瑚
骨董品
古銭
書道具
切手
アンティーク家具
べっ甲
時計・貴金属・宝石
古書