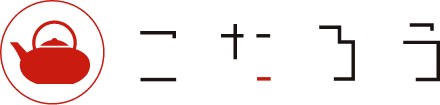志野というやきもの/川端康成・荒川豊蔵・鈴木蔵・魯山人

●川端康成と志野
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」
誰にでも書けそうな簡単な文章であるが、書きだしの文章としては実にインパクトがある。ご存じのとおり、川端康成の小説「雪国」の冒頭である。今年は川端康成の没後50年であった。ノーベル賞受賞者のガス自殺という衝撃的な出来事から50年もたってしまった。川端の小説で一番知られている小説は「伊豆の踊子」であろうが、「千羽鶴」という小説がある。この小説のなかには、志野の茶碗・水指が登場しており、主人公が登場人物の母娘の姿を志野に思い入る場面がある。川端は日本の美を新たな感覚で表現している。川端を魅了した志野とはどのような焼物であろうか。
●志野と長石
志野は桃山時代に完成された焼き物として知られている。中国が磁器という白い焼物を手に入れたのに対し、日本人が作り出した白い焼物が志野である。
中国の磁器が白い素地の焼物であるのに対し、志野は釉薬が白い焼物である。志野釉の原料は長石という鉱物である。現在の精製された長石では、他の材料を添加しないと容易に溶けてくれない。一方、昔の志野で使用されていた長石は風化長石というもので、長石を含む岩石が風雨などにより長時間かけて分解され、長石分が取り出しや良くなったものである。この風化長石には多少の他の物質が含まれており、陶器の焼成温度で溶かすことが可能なものである。長石自体は木灰を入れることで長石は容易に溶けるのではあるが、その場合、白い色は濁っていくので、志野には基本的には使用されていない。

●志野の緋色
志野の特徴として、釉薬の表面に浮かぶオレンジ色の緋色が挙げられる。この緋色は鉄分が釉薬の表面上に浮かび上がったものである。その鉄分自体は陶土の持つ鉄分である。先の当ブログでも紹介しているが釉薬が解け始めるのは施釉された表面ではなく、陶土に接した部分である。したがって、釉薬全体が解けるにしたがって、表面近くまで浸透してくるものと推察される。現在でも、志野の焼成に数日の長時間を掛けるのは、こうした緋色の生じるプロセスが必要とされるからである。単に釉薬を溶かすのであれば、高めの焼成温度によって短時間で可能であり、この場合単に白い焼物、もしくは含まれる鉄分や他の原料によるわずかな着色が生じる焼物となる。
岐阜県多治見出身で後に、志野・瀬戸黒で人間国宝となる陶芸家・荒川豊蔵もこの緋色を生み出すプロセスには苦労している。実際に、荒川が用いた緋色を生むやり方は、志野を焼成するときに使用する耐火性のあるサヤという容器の内側に鬼板という鉄分の多い鉱石や鬼板の泥を塗りつけ、サヤの中に入れた作品の釉薬表面へと気化した鬼板の鉄分の緋色を移す手法を多用した。そのため、荒川の志野にはサヤの鬼板が釉薬表面に貼りつくことがあり、焼成後に取り除いた跡の見える作品がある。
荒川に次いで、志野の人間国宝となった鈴木蔵は現代の技術で志野を追求している。鈴木の着眼点はあくまでも陶土の鉄分を緋色へと転化させることに集中している。鈴木は緋色の発生要因として、釉薬が解けてからの冷却プロセスに着目した。鈴木はガス窯を使用しているが、その壁面は1mにも達する厚さになっている。これは釉薬が解けてから冷めていく状態を長時間キープしておくことが緋色を生じさせるには肝要であるという考えである。

●志野の誕生地を求めて
江戸時代から愛知県瀬戸地方の窯業の発展により、瀬戸焼の代表的な技法である志野焼も瀬戸の陶工によって生まれたものと思われていた時代があった。
昭和初期、さきに紹介した荒川豊蔵は魯山人の工房で働いていた。1930年、荒川は魯山人に帯同して名古屋に赴いた。その際、古陶磁の蒐集家から筍の絵付が浮かぶ志野の筒茶碗を見せてもらった。この時、荒川はピンと来るものがあった。それは高台の内側にリング状にわずかに残った赤い土であった。この土は陶器を焼成するときに窯道具と器の間に入れて、高台が融着するのを防ぐためのスペーサーのようなものである。この赤い土は瀬戸に使用例はなく、荒川の生地である美濃地方の焼物に使われる例があったことを荒川は知っていた。

その後、魯山人の元を辞した荒川はこの志野の痕跡を求めて、美濃の窯跡を探し回ることにした。その結果、可児市大萱の窯跡で、名古屋でみた茶碗と同じ筍の絵付がされた志野の破片を発見するに至る。これを契機に志野をはじめとする桃山陶の織部・黄瀬戸・瀬戸黒は美濃地方で生まれた焼物であると認められるようになっていった。さらに荒川はその大萱の地で窯を築いたのである。
\画像を送って待つだけ!LINEで無料査定を希望の方はこちら/
URL:https://kotto-kotaro.com/line/
\メールで無料査定を希望の方はこちら/
URL:https://kotto-kotaro.com/assessment/
WEBからメール、LINEで簡単査定! 24時間受付中!お気軽にどうぞ!
お問い合わせ・ご予約 店舗電話受付時間 9:30-18:00 0120-922-157
関連記事
買取実績
こたろうの買取品目一覧
絵画
掛軸
茶道具
陶器・磁器
中国骨董品
刀剣・日本刀・武具
工芸品
漆器
彫刻
木工品
西洋アンティーク・西洋陶器・西洋美術品
珊瑚
骨董品
古銭
書道具
切手
アンティーク家具
べっ甲
時計・貴金属・宝石
古書