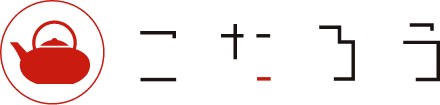つぼ・壺・壷と甕・瓶/土器・せっ器・六古窯

●壺とは
古くは縄文時代・弥生時代から作られていた壺。起源でいえば鉢状の口が細くなっていないものが先に作られたものではあるが、保存性を考えて口が細くなっていったようである。
平安時代・鎌倉時代のいわゆる六古窯で数多く作られていたものもまさに壺であり、後世に茶道具として出世したものも多くある。
さて、この六古窯の頃に作られていた壺を見ると、底の面積は胴体に比べてかなり小さく、胴部から底部にかけて絞り込まれており、実に不安定に見える。しかし、なぜこのような形状にしたかというと、実は地面に置いて使うときは、この下部の形状のように穴を掘り、半ば埋めて使っていたので、決して倒れることなく、不安定なものではなかったようである。では、窯で焼くときはどうかというと、初めから倒して置いたり、口を下にして上下逆さまにして焼成したものがあると思われる。
現代の目で見ると、この不安定に見えるバランスが実に面白く見え、置物としてそのまま置いていても実に風情な古陶である。

●甕とは
壺より大きく、主に水などの液体や酒・発酵物の製造・貯蔵に使用していたのが甕である。壺との違いについて正確な基準はないが、移動や据え置きなどの際に二人以上の人手が必要な大きさのものが甕である。壺とは異なり、甕には口の狭まったものはない。ほぼ広口といっていいものである。
古代当初はもちろん土器や素焼であったが、高温長時間の焼き締め(せっ器)や釉薬の開発によって近代まで主要な容器として重宝されていたのが壺と甕である。近代において、金属やプラスチックなどの樹脂製品の容器が開発されるまでは、防腐性・耐酸性などの観点で木製のものよりすぐれていたが、未だに好んで貯蔵に甕を使用する方もいる。
実はこの甕は縄文時代には人間の埋葬用として用いられていたものがある。しかし、江戸時代のものとみられる備前焼の大甕が、埋葬(土葬)用に使用されていた例もあり、古備前の大甕を買い求める骨董好きな方は要注意である。

●日本人の生活と壺・甕
日本人の生活に傍らにあった壺であるが、特に出世したのが、茶道における花器への転用である。信楽や伊賀などで作られた「蹲」という小型の壺は、人がうずくまっているようなずんぐりした姿から名付けられた壺である。この「蹲」は茶道具の花器として人気がある。また、越前や備前で作られる「おはぐろ壺」は、両耳と注ぎ口がついた小さな壺であるが、これはおはぐろの用途がなくなったが、やはり花生として使われている。
やはり壺が大きく変化したのは、江戸時代に生け花が流行して、花器としてのニーズが高まり、物入れの壺から花瓶へと出世していったのではないかと思う。たしかに、たとえ同じ形状であっても、壺という名称より花瓶という名称の方が、優雅に聞こえる。
●壺にまつわるエトセトラ
「壺算」という落語がある。実はあの漫画「ドラえもん」でも、この落語をアレンジしている話が描かれている。もとの落語は以下のような内容である。
大阪に住むある旦那が、壺(大きいもののようなのでむしろ甕がイメージされる)が割れたので、新しい壺を買いに行くように言いつかる。また、割れた壺の倍のサイズを買うように頼まれたという。途中、立ち寄った友人の旦那が一緒についていくことになった。店にいくと、この友人の旦那は、何を思ったか、元のサイズの壺を三円で買ってしまった。壺を頼まれた旦那本人も、訳が分からず天秤棒に括りつけた壺を友人とともに担いで帰り始めた。しかし、その友人が倍のサイズを買わなければと、元の店に戻った。店の番頭の話では、倍のサイズの壺はやはり買った壺の倍額・六円だという。すると、その友人は「ではこの壺を三円で下取りに出そう。先に、三円払ってあるから、これで六円の壺はもらっていくよ」と、倍のサイズの壺を運び始めた。合点がいかない番頭であるが、算盤で計算すると、なんどやっても三円+三円でどうしても六円となってしまう。もちろんこれは「下取り」ではなく、「返品」であるから三円を返せば済むことであるが、混乱した番頭はついにそのまま倍のサイズの壺を持ち帰らせてしまった。あとで、その友人がつぶやく。「こっちの思う壺や」・・・。
ところで、この「思う壺」は何かというと、サイコロ賭博で使用するカップを伏せたような籠のことだそうである。我々がイメージする壺とは異なる。
また、アニメ「ハクション大魔王」で魔王が出てくるところは、どう見ても花瓶のようであったが、正しくは「魔法の壺」とのことである。
もうひとつ蛇足だが、笑いが止まらなくなる「笑いのツボ」は「壺」ではなく、鍼灸・東洋医学でいうところのツボ・経穴とのことらしい。つまり、ツボが刺激されて、笑いが活性化するという意味なのである。
\画像を送って待つだけ!LINEで無料査定を希望の方はこちら/
URL:https://kotto-kotaro.com/line/
\メールで無料査定を希望の方はこちら/
URL:https://kotto-kotaro.com/assessment/
WEBからメール、LINEで簡単査定! 24時間受付中!お気軽にどうぞ!
お問い合わせ・ご予約 店舗電話受付時間 9:30-18:00 0120-922-157
関連記事
買取実績
こたろうの買取品目一覧
絵画
掛軸
茶道具
陶器・磁器
中国骨董品
刀剣・日本刀・武具
工芸品
漆器
彫刻
木工品
西洋アンティーク・西洋陶器・西洋美術品
珊瑚
骨董品
古銭
書道具
切手
アンティーク家具
べっ甲
時計・貴金属・宝石
古書