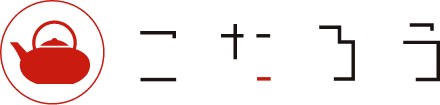東の魯山人、西の半泥子・・・川喜田半泥子 茶碗

その日、アメリカのワシントンDCから来日した商談相手は帝国ホテルに宿をとっていた。
日比谷通りのエントランスから入り、メインホールを抜け、地下へと降りる。
「タワー」と呼ばれている新館の地下一階の奥にてんぷら店「天一」がある。
10数時間のフライトの直後で連れまわすのは気の毒だと思い、彼を館内のこの店に招いたのである。
デパートにある店舗と比べ、さすがにこじんまりとした印象。しかし、ランチ天丼しか食べたことのない身にとっては、この日のカウンター越しに提供される揚げたての天ぷらはこの上なくおいしく感じた。
その一方で、手元の受け皿が気になる。
グレーの素地に鉄絵。
その皿は、だれぞやの唐津か?、乾山写しか?
料理がはけたところで、思い切って引っ返してみる。
うらには(廣永)の印銘。
「廣永窯・・・」とつい声が出る。
すると、揚げていた職人が「川喜田半泥子さんに懇意にされていた縁で、廣永窯さんのものを使わせていただいています」と声をかけてきた。
廣永窯は半泥子の使用していた窯場を引き継いだ工房で、弟子として半泥子を助けた続けた坪島土平を中心に、この当時は数名の職人とともに作品を生み出していた。(正確に記せば坪島土平の「土」には右棒の間に「、」が入る文字)
さらに時は経て、半泥子の死後から約50年が過ぎた。工房を引き継いだ坪島土平も鬼籍に入り8年経過した。しかし現在でも後を継ぐ職人によって廣永窯は続いている。
昭和から平成、そして令和へと、半泥子の魂は生き続けている。

「東の魯山人、西の半泥子」と比較される二人の巨匠。
現在の美術業界において、取引される作品の価格はその高さにおいて正に双璧である。併せて、元々本職の陶芸家でないことも両者に共通している。
ただ残った作品でみると、魯山人はみずからの思いに沿う形を追求したのに対し、「おれはろくろくのまわるまま」と素材である陶土が自然となす形を好んだ半泥子と、やや対照的だ。
魯山人は職人がロクロを挽いたものに手を加えて完成形にしたという。また焼き上がりの変化が乏しい備前焼は一面銀彩を施して備前焼とはまったく異なるものに仕上げた。「器は料理の着物」という意に沿うものに仕上げたのが魯山人である。
一方、半泥子はロクロの回転から伸びてくる陶土の動きを楽しみ、それを生かした。ロクロだけでなく、高台の削りや加飾、窯焚・焼成までそれぞれのプロセスが生み出す器の景色を楽しんだ。結果、縁が切れたり、中心がずれたり、傾いたり、割れたり・・・。しかし、それもこれも我なり、と楽しみ、自らその作品に銘もつけた。
一見すると、粗雑で、素人の作品にも見えるが、今だ半泥子の作品は多くの人を魅了する。その理由はなぜだろう。
小説家・城山三郎の作品に「粗にして野だが卑ではない」という小説がある。第五代国鉄総裁・石田禮助を主人公にした小説である。半泥子の作品を見るたび、このタイトルが思い出される。
半泥子の人となりが石田禮助と重なる訳ではないが、半泥子作品の印象は「粗にして野だが卑ではない」と見えるのである。
「粗にして野」な作品はある意味では誰でも作ることができる。陶芸でいえば、初心者の作品はおいおいこのようになる。また、陶芸家でなくとも「粗雑」なことが自己表現と考えるアーチストをよく見かける。
作られた作品が「卑」であるかどうかは、評価・見る者の「好み」の要素が強いとは思いつつ、やはり「卑」なアートが気にならない訳ではない。
ある面では「過度な作為」が「卑」か「卑でない」かの分かれ目になるような気がするが、「過度」という基準はどの程度なのかという答えはない。
でも半泥子の作品は、「粗野に見えても、卑ではない」と感じる人が多いのではないか。
そして、それが見る人の心を惹きつけるのではないか、と思うのである。
縁あって、最近、あるお客様から半泥子の水指をお譲りいただいた。
玉縁の一重口で、ロクロ挽のあと、四方に形を歪めてある。
半円形に弧を描く釘彫のススキ。
鉄絵の具を打ち付けたような桔梗(?)。
縮れた釉薬。
半泥子らしい傑作である。
やるな!無茶法師! と誰もが思う名品。
関連記事
買取実績
こたろうの買取品目一覧
絵画
掛軸
茶道具
陶器・磁器
中国骨董品
刀剣・日本刀・武具
工芸品
漆器
彫刻
木工品
西洋アンティーク・西洋陶器・西洋美術品
珊瑚
骨董品
古銭
書道具
切手
アンティーク家具
べっ甲
時計・貴金属・宝石
古書