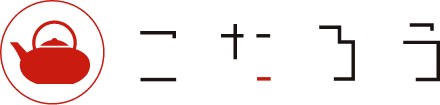「揚州八怪」って?


「揚州八怪(ようしゅうはっかい)」とはなんぞや??
大阪市立美術館で開催の展覧会の題名である。
折りしも大阪では「あやしい絵展」という展覧会も開催中、怪しい生き物かなにか?まさかねーと、まずその聞きなれない言葉にひっかかった。
なになに、「揚州八怪」とは、中国の清朝18世紀に揚州を舞台として活躍した、個性豊かな書画家8人をまとめた呼び名である。八怪の「怪」は、「並外れて素晴らしい」というポジティブな意味で使われるそう。(後世「八怪」と呼び批評家によって15人ぐらいになる)
塩商の活躍によって経済的に活況を呈した揚州には、たくさんの芸術家たちが集い、競うようにその才能を花開かせたという。
展覧会案内の写真には衝撃を受けた。こんな字が300年近くも以前に書かれていたとは!
書の展覧会は正直今までは足を向けていなかった。まず読めないことが多くよくわからない、面白く感じられなかったからである。
二十代のはじめ、私に古美術のいろはをご教示下さったK先生は代々古美術商のお家であり、著名な茶道コレクションを有する美術館の学芸員もしておられた。
歩く百科事典と称されるくらい知識豊富、著作物も多く、陶芸、漆芸、絵画、古筆など古美術品のみならず茶道、華道をはじめとした古今東西の諸事に通じておられた。
「物がわかるようになるのにはとにかく本物を観なさい。何度も観なさい。贋物をいくら観ても真贋がわかるようにはならん。知識も大事、しかし知識が邪魔になることがある。贋物にひっかかる。いいか悪いかが感覚として捉えられるようになって、はじめて真贋がみわけられる。この感覚は教えて教えられることではない」
学問だけでなく、古美術品の売買をされてこられた先生の、私にとって根底となった大切な教えである。
その先生が「今は古筆を愛でている時が一番心がやすまる」とあるときおっしゃった。そんな境地に達するのはいつのことだろうとそのとき思ったものだが、進歩のないまま時は過ぎた。
2014年 東京国立博物館で「台北 國立故宮博物院 -神品至宝-」が開催された。
門外不出の名品・翠玉(ひすい)でできた「翠玉白菜」が大人気で行列ができた展覧会だ。台北の故宮は以前2度たずねてはいる。汝窯の青磁輪花碗など名品揃いの会場を人混みを避けながらいくと、思いがけないところで釘付けとなった。
蘇軾(そしょく)筆 「行書黄州寒食詩巻」北宋時代・11~12世紀
47歳の蘇軾が、黄州に左遷されていた時の詩である。
はじめて書に感情を動かされた。蘇軾の思いの凄まじさが横溢している。読めているわけではないけれど書を追っていくと胸が締め付けられた。
傑作といわれているのだから当然なのだろうが、私にとって忘れられない体験となった。
今回「揚州八怪」展で最も興味を持った書は、金農(きんのう)「隷書六言詩横披」清・乾隆27年(1762) 東京国立博物館蔵である。
筆を刷毛状に用い、横画と縦画の太細を極端につけて、ときに左払いをヒゲのように細長く伸ばす。活字のゴシック体を連想させるデザイン的な独特の書風にまず目をひかれたのだが、よくみていくとその抑揚に心のうちが滲みでてくるような味わいがある。強烈な個性がある。
漆の刷毛で書いたようにみえることから漆書(しっしょ)とよばれるそう。
金農は幼少より詩文に長じ若くして名をなし、考証学も学んでいた。
終生士官を好まず、中年以降は各地を漫遊し、晩年揚州に定住。貧困にさいなまれながらも詩文や書画を楽しむ日々を送ったという。

そのほか、秀麗な書風だった高鳳翰(こうほうかん)は、55才で利き手の右手がリュウマチで使えなくなりその後左手で書いた。その書はかえって豪放磊落、風趣に富み好まれた。


今回展示されているどの書画も自由でおおらか、新しいことを試みる創意工夫があり、その洗練された筆墨に心が沸き立った。人生楽しいことばかりではない辛いことだってあるが、楽しんで生きようよと時代を場所を超えて、語り掛けてくれた。
読めるようになりたいと仮名文字の稽古はしているが、遅々として進まず、まだまだ、まだである。でも、読めずともいいなあと、おぼろげながらにも感じられるようになったかな。道は遠いが、遅まきながらのたのしみである。
関連記事
買取実績
こたろうの買取品目一覧
絵画
掛軸
茶道具
陶器・磁器
中国骨董品
刀剣・日本刀・武具
工芸品
漆器
彫刻
木工品
西洋アンティーク・西洋陶器・西洋美術品
珊瑚
骨董品
古銭
書道具
切手
アンティーク家具
べっ甲
時計・貴金属・宝石
古書