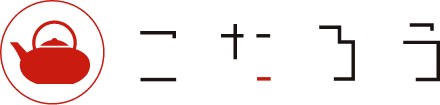泣きたくなるほど、おもしろい

7月14日に選考・発表された第165回直木三十五賞者は二名となった。
その一人、澤田瞳子氏の受賞作は「星落ちて、なお」である。
この作品の主人公は河鍋とよ、という女性。河鍋暁翠という号を持つ画家にして、河鍋暁斎の娘である。
小説は河鍋暁斎の臨終の場面から始まる。その後、とよの半生数十年が描かれている。つまりタイトルの「星」とは河鍋暁斎のこと。
とよは暁斎から将来を嘱望され、五歳の時に暁斎から「鳩に柿図」という絵を手本として与えられた。その手本は彼女の画業の道標となり、終生この手本画を大事にしていたようである。とよの死後も、この手本画は遺族・子孫に引き継がれ、残されている。
2008年春、京都国立博物館で開催された暁斎の没後120年記念展では「絵画の冒険者」と題された彼の画業を網羅した展覧会となった。
犯罪者として捕らえられた原因となる戯画や風刺画、浮世絵、幽霊画、仏画、花鳥画、美人画、挿絵・・・。様々な絵が次々と展開する展示構成。展示会パンフレットのコピー、「泣きたくなるほど、おもしろい」と思える作品の数々が展示された。
ちなみに、当時編集子は住いのある埼玉から日帰りで京都へと、この展覧会を観覧しに出かけた。もっとも、同時期に京都市美術館で開催していた「秋野不矩展」も併せて観覧できるということもあって急遽日帰りで出向いたのだが、この時に購入した両展の図録が厚く、またやたら重く、帰路は拷問のように感じた記憶がある。
2018年に亡くなった「キャバレー王」と呼ばれた実業家・福富太郎氏も河鍋暁斎のコレクターとして有名だった。
福富氏と河鍋暁斎作品との出会いは骨董屋で買った書棚におまけとして付けてくれた二本の掛軸。文学者・翻訳家の奥野信太郎氏がその掛軸を見て、福富氏にかけた言葉が「鳥を描く名人。今は一羽一万円だが、最後には一羽百万円になる」とのこと。この会話がいつの話で、当時と現在の評価額が正しいかどうかは不明だが、このように河鍋暁斎が忘れ去られていた時代があったということは事実である。

福富氏はその後、河鍋暁斎のコレクションに力を注ぎ、河鍋暁斎の展示が必要な展覧会などは、彼のコレクションが貸し出された。もちろん、2008年の京都国立博物館での展示でも、同氏のコレクションが貸し出されて、多くの観覧客を楽しませた。
また、昨年末から今年2月まで、東京駅のステーションギャラリーで「河鍋暁斎の底力」という展覧会が開催された。この展示は、河鍋暁斎の下絵や素描、絵手本などに絞り、すべての本画を除く作品だけで構成されるという、異色の展示であった。河鍋暁斎の本画は彩色段階において、弟子たちの手が入ることがある一方、この回の展示作品はすべて河鍋暁斎のみの手によるものだけが展示された。
河鍋暁斎の絵と出合い、20数余年。さまざま展示会通して、多数の絵を見てきたが、「河鍋暁斎はコレ」という答えはでない。河鍋暁斎とほぼ同時期の画家として狩野芳崖がいる。彼の代表作にして絶筆「悲母観音」、彼の作風は狩野芳崖という名前とともに多くの方は思い出すことができると思う。一方、河鍋暁斎はというと、「これぞ河鍋暁斎」という作品は、河鍋暁斎をよく知る人それぞれで異なり、また他人に説明することは難しいであろう。
しかし、それゆえに各自の中で、「河鍋暁斎はコレ」というのが自分で見つけることができるのかもしれない。編集子にとっては河鍋暁斎というと、カエルを描いた「鳥獣戯画」であり、幽霊の絵である。
河鍋暁斎記念館という小さな美術館が埼玉県蕨市にある。今は曾孫の河鍋楠美氏が館長を務める美術館で、河鍋暁斎作品の収集と管理、研究をおこなっている。もともとは同氏が開設していた眼科を改築した建物で、個人宅のような美術館である。
最寄り駅でいうと、JR西川口駅と蕨駅の中間。かつて、この西川口駅周囲には風俗店が多数あることで知られ、若かりし頃は、そうした店へといくと思われそう、と下車するものなんとなく気恥ずかしく思った。いまでこそ関東地区では「住みたいまちランキング」で上位となる埼玉県川口市で、「今は昔・・・」の感がある。
その河鍋暁斎記念館は河鍋暁斎の作品と間近に向き合える美術館として、今も我々を迎えている。
皆様も河鍋暁斎の作品とよき出会いを・・・。
関連記事
買取実績
こたろうの買取品目一覧
絵画
掛軸
茶道具
陶器・磁器
中国骨董品
刀剣・日本刀・武具
工芸品
漆器
彫刻
木工品
西洋アンティーク・西洋陶器・西洋美術品
珊瑚
骨董品
古銭
書道具
切手
アンティーク家具
べっ甲
時計・貴金属・宝石
古書