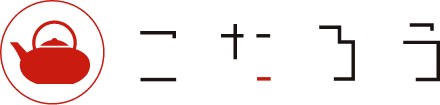絶対的技術脈々と・九谷赤絵/福島武山・見附康文/羽生結弦

●技術と芸術・羽生結弦の信念
2022年・北京オリンピック、二大会を制したフィギュアスケートの羽生結弦は四位に終わった。前大会以来のゴールとしていた四回転半ジャンプは失敗ながらも予定通り行われている。前回大会の平昌オリンピック後、2018年2月27日に日本記者クラブで行われた記者会見で、四回転半を含むジャンプへの取り組みについて問われると、羽生は次のように述べている。
「芸術は絶対的技術に基づいたもの」
これはフィギュアスケートの中でジャンプが高度化していく中、一方で芸術性が失われるのでないか、という説に対して持論を述べた中での言である。つまり、難易度と芸術性は両者のバランスではなく、「技術の延長線上に芸術がある」という意味である。逆に言えば、技術がなければ芸術ではないのである。
●九谷焼の発祥と赤絵細描
江戸時代中期に後藤才次郎という陶工が、有田焼の技術を盗み出して始まったのが北陸石川県の九谷焼とされるという説がある。日本陶磁器史上では古九谷様式という有田焼きの一様式に過ぎないとする説が学問的には主流となっており、発祥については疑義が残されているが、九谷焼は今日まで脈々と続いている。そのなかに、赤絵という技法がある。赤絵という技法自体は日本各地に存在する。一番有名なものは有田の柿右衛門である。しかし、京都でも野々村仁清らによって赤絵の技法は生まれている。九谷の赤絵は京都の青木木米と永楽和全の指導によってその礎がもたらされた。九谷焼の技法に「飯田屋」「八郎手」と呼ばれるものがある。赤絵をベースに細筆精緻な絵付けをしている作品である。発祥はともかく「古九谷」と呼ばれる五彩の上絵作品とともにこの「飯田屋」に端を発する赤絵細描は九谷焼の中で大きな流れとなっていく。特に、幕末から明治時代にかけて輸出産業が興ってくると、赤絵細描の作品は大きな役割を果たしている。実際に明治20年には、有田・瀬戸を抑えて九谷焼が輸出陶磁器のトップシェアになっていたそうである。しかし、その後は輸出陶磁器自体が恐慌や戦争によって衰退し、手の込んだ赤絵細描の九谷焼は細々となっていった。

●九谷焼の技術
明治時代には重要な産業として九谷焼は捉えられておりその絵付職人が多数生まれている。特に初代中村秋塘や竹内吟秋と浅井一毫の兄弟らの作品は、古美術市場で近代九谷焼の赤絵細描作品として注目されている。こうした絵付け職人の育成自体も明治時代は県を挙げて取組んでおり、五級から一級までの認定制度が存在していたという。
しかし、特に第二次世界大戦後はこうした職人は影を潜め、個人作家の時代に突入するにつれ、赤絵細描の作品は注目されなくなっていたようである。この時代について編集子はいくつかの文献を当たってみたが、赤絵細描の職人たちについての記録はない。もっとも二代須田青華のように赤絵細描を得意としていた陶芸家がおり、技法が途絶えたというわけではない。

●赤絵細描の今、福島武山
昭和後半から、平成中期までは九谷焼は五彩の陶芸家の世界であった。人間国宝となった三代徳田八十吉、文化勲章受章の浅蔵五十吉など五彩や色釉を中心とした陶芸家であり、赤絵細描のような精緻な技法はとっていない。古美術市場においても、希少性から五彩の古九谷が最高値で取引されていた時代であった。
昭和46年、妻の実家の家業である九谷焼の絵付に触れ、絵付師を目指した人物がいる。現在の赤絵細描の最高峰・福島武山の誕生である。古陶の赤絵作品を研究した福島は赤絵細描の技術を突き詰め、後発ながら九谷焼の研修所で赤絵を指導するまで技術を蓄え、九谷焼・赤絵細描のトップランナーとなる。福島に師事した見附正康は元サッカー日本代表・中田英寿に見いだされ一躍脚光を浴びた陶芸家である。福島もフランスのエルメスから文字盤製作の依頼を受けるなどして、赤絵細描の技法は今や九谷焼の牽引車となっている。
赤絵細描自体は古典的な技術である。ただし、現在、福島や見附が使用する技術は図案の一部に古典的な要素は残るが、絵具や道具までを含め、昭和から平成にかけて育ててきた21世紀の技術となっている。その技術によって、九谷焼は芸術性の高い陶磁器として現代人の心を掴んでいる。
このように記していくと、九谷焼は上絵の歴史のように思えてくるが、実は九谷焼は分業の上に成立している。器体を作る轆轤師がいる。場合によっては、下絵を器体に描く職人もいる。さらには九谷焼の拡販に努めてきたプロデューサーたる販社・商社の存在も忘れてはならない。
\画像を送って待つだけ!LINEで無料査定を希望の方はこちら/
URL:https://kotto-kotaro.com/line/
\メールで無料査定を希望の方はこちら/
URL:https://kotto-kotaro.com/assessment/
WEBからメール、LINEで簡単査定! 24時間受付中!お気軽にどうぞ!
お問い合わせ・ご予約 店舗電話受付時間 9:30-18:00 0120-922-157
関連記事
買取実績
こたろうの買取品目一覧
絵画
掛軸
茶道具
陶器・磁器
中国骨董品
刀剣・日本刀・武具
工芸品
漆器
彫刻
木工品
西洋アンティーク・西洋陶器・西洋美術品
珊瑚
骨董品
古銭
書道具
切手
アンティーク家具
べっ甲
時計・貴金属・宝石
古書