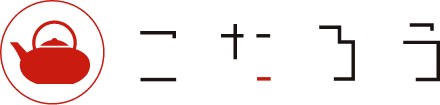青木木米/三十にして立つ 京焼 再興九谷焼 春日山窯 呉須赤絵 観音像 奥田頴川 田能村竹田

●九谷に残る木米の足跡
金沢の骨董店を覗くと、「木米」銘の作品をいくつも見かける。木米とは京都出身の陶工・青木木米のことである。残念ながら、本人作とは認められない作品であるが、木米の銘が高台にしっかりと書かれている。
木米が金沢に招聘されたのは、江戸時代の後期1807年であった。いわゆる古九谷を製造していたとされる窯が廃れた後、藩主の命により作られた春日山窯の指導者として招かれた。しかし、金沢城の火災により藩の財政が悪化し、藩の庇護を失い、民間の窯元となったことで、木米の関心は薄れ、1808年には京都に戻ることとなった。
わずか2年足らずの滞在で、当然木米本人の作品は多くは生まれるはずがなく、石川・金沢に現存する木米銘の作品のほとんどは写し・模造の作品となる。そして、九谷焼の「木米」銘のブランドとして定着したのである。実際に今でも木米風の作品は売られている。白い素地に赤絵の塗り、人物を描き込んだ呉須絵写しのものがである。多数の唐子を描き、その楽しげな姿は石川県民に愛されたのである。いわば「木米焼」である。
この木米によりもたらされた呉須赤絵を基本とする色絵の技術は、木米のいない加賀の地において、後の若杉窯や宮本窯へと引き継がれていったことは事実である。こうして、木米は今も残る石川県の九谷窯元に大きな影響を与えたのであった。
●青木木米とは
1767年、京都の茶屋に青木木米は生まれた。幼名は「八十八」。
文人画を学ぶ傍ら、29歳のとき文人・木村蒹葭堂と知り合い、彼の書庫で清の朱笠亭が著した『陶説』に出会う。この陶技書を読んだことが、作陶を志すきっかけとなった。その後、京焼の名工・奥田頴川に入門し、30歳で京都・粟田口に窯を開き独立した。
作品は煎茶器を主に制作している。白磁、青磁、赤絵、染付などその作域は幅広く、特に中国古陶磁への傾倒から、中国物の写しに名品を残している。
「木米」の号は、生家・青木から「木」の一字と名「八十八」を「米」字にまとめて「木米」としたようだ。
晩年は聴力を失ったことから、「聾米」と号するようになった。そのきっかけは、陶磁器の焼成時に窯のそばに耳を近づけ、窯から聞こえる音により、焼成具合を判断したためだと言われている。
1833年に死去。
木米は、十一代永樂善五郎保全、二代高橋道八・仁阿弥道八とともに京焼の幕末三名人と呼ばれた。野々村仁清、尾形乾山から続く京焼の基礎はこの三名によって確立されている。
●文人として生きる
30歳から陶芸を始めて、名工として称されるようになるにはどれだけの努力が必要となるのであろう。九谷招聘に先駆け、1801年に紀州藩・和歌山に作陶の指導者として招聘されている。開窯した30歳となった1797年からわずか4年後である。さらに九谷・春日山窯に招聘されたのが40歳のときであるから、いずれにしても開窯から10年ほどで指導者としての実力を備えたのである。天賦の才もあるであろうが、陶芸を学んで体得するまで集中力は計り知れない。
木米の集中力を儒学者・頼山陽は次のように述べた。
「私は天下の書物で読まないものはなく、天下のことで知っていないことはない。しかるに爺(木米)は私のまだ読まない書物を読み、また私の知っていないことを知っている」
とはいうものの、木米はけっしておかたい人物ではない。
親友であった画家・田能村竹田は次のように述べた。
「木米の話は諧謔を交え、笑ったかと思えば諭す、真実かと思えば嘘というように、奥底が計り知れない」と。
晩年には、頼山陽・竹田・僧の雲華・蘭方医の小石元瑞たちと、親交した当代一流の文人・木米であった。年若い彼らの中にあって、青木木米は「識字陶工」として博識、かつ知的なユーモアにあふれた大人と尊敬されていたのであろう。
ただ、木米自身は陶工として最期を迎えるのを望んだ。
田能村竹田は、晩年の木米が次のように語ったと伝わっている。
「これまでに集めた各地の陶土をこね合わせ、その中に私の亡骸を入れて窯で焼き、山中に埋めて欲しい。長い年月の後、私を理解してくれる者が、それを掘り起こしてくれるのを待つ」
骨董品買取こたろう|確かな目利きで高額査定。現金買取・全店最短即日対応・全国対応
\画像を送って待つだけ!LINEで無料査定を希望の方はこちら/
URL:https://kotto-kotaro.com/line/
\メールで無料査定を希望の方はこちら/
URL:https://kotto-kotaro.com/assessment/
WEBからメール、LINEで簡単査定! 24時間受付中!お気軽にどうぞ!
お問い合わせ・ご予約 店舗電話受付時間 9:30-18:00 0120-922-157
関連記事
買取実績
こたろうの買取品目一覧
絵画
掛軸
茶道具
陶器・磁器
中国骨董品
刀剣・日本刀・武具
工芸品
漆器
彫刻
木工品
西洋アンティーク・西洋陶器・西洋美術品
珊瑚
骨董品
古銭
書道具
切手
アンティーク家具
べっ甲
時計・貴金属・宝石
古書