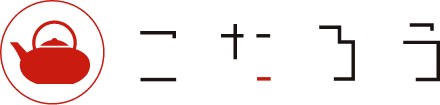オブジェ焼・走泥社/八木一夫・鈴木治・熊倉順吉・藤本能道・十二代三輪休雪 走泥社再考

●1950年 ニューヨーク近代美術館
第二次世界大戦中、灯火管制により一部の地域では途絶えた窯焚の炎は終戦後に再び灯った。資源的には乏しい時期ではあったが、陶工たちは再び陶磁器の作成に注力していく。
敗戦から五年、アメリカのニューヨーク近代美術館では敗戦国である日本の陶芸作品・花器四点を購入し、展示している。作者の名前は八木一夫、当時32歳になる若手陶工であった。京都の陶工であり、父親は中国陶磁の写しで名を馳せた八木一艸。一艸は大阪出身だが、京都の陶磁器試験場で学び、清水焼で知られる五条坂に開窯していた。八木一夫はその二代目となる。
ニューヨーク近代美術館の収蔵前に八木一夫は大きな転機を迎えていたのである。

●走泥社起つ
戦後まもなくの1948年に八木一夫は走泥社という陶工のグループを結成している。八木のほか、鈴木治、山田光、松井美介、叶哲夫という京都で作陶する四名の陶工がメンバーとして参加している。
京都という土地柄や京都人というと「伝統」「保守」というようなイメージが強いが、一方では「新しい物好き」「革新派」というような一面もあるという。この八木たちの走泥社はまさに後者を突き進む前衛的な陶工集団である。当初はピカソ、クレー、ミロなどのシュールレアリズム絵画的な要素を持つ陶芸作品であった。しかし、その後、イサム・ノグチの来日により、表面的なモダンさにとどまらない本質的な造形意欲に駆り立てられる。それが「オブジェ焼き」という陶芸作品の方向性へ収束していくことになった。
●オブジェ焼き
20世紀の西欧近代美術において「オブジェ」という造語が生まれる。もともとは「Objet/フランス語で《物体・対象の意》。派生的に前衛芸術で、作品中に用いられる石・木片・金属などさまざまな物。また、その作品」ということである。また、さまざまな定義がされており、たとえば漂流物・流木といった自然界に存在する人工的に手を加えられていないものまで含める場合があるという。
なかなか難解ではあるが、編集子なりに解釈すると、用をたす目的で制作されたものではないもの、存在だけでアートであると判断できるものと考えた。対極的に存在するものが民芸であり、用をたす目的でないものはアートであろうとも民芸には含まれない。
話を八木に戻すとして、八木は1954年、彼の代表作と誰もが認める「ザムザ氏の散歩」という作品を発表した。陶土を管状にしてリングを作り、そのリングを垂直に立てた状態から短いの手足のようなものが伸びている作品である。もともとカフカの小説『変身』を題材にしたとのことで、小説の主人公が一夜にして昆虫に変身したことを表現した作品とのことである。これが「オブジェ焼」と八木が称した陶芸作品のはじまりとなる。

●八木一夫の死と走泥社の解散
その後、八木は黒陶という漆黒の陶器に取り組む。当時、彫刻家としてテラコッタ/土器に取り組み始めた辻晋堂と木内克らによる陶芸と異なるアプローチとして取り組み始めたのが黒陶である。さらには、信楽焼で土管、壺なども作成した。1971年には京都市立芸術大学美術学部教授に、1972年札幌オリンピックのメダルのデザインを共同担当した。そして1979年、心不全のため急逝した。
一方、集団活動としての走泥社はメンバーの入れ替わりがありながらも、八木の死から約20年後の1998年まで存続していた。京都の陶芸家・熊倉順吉や林秀行らがメンバーとなり、最大30名ほどのメンバーが所属していた時代があった。色絵磁器で人間国宝となった藤本能道はかつてこの走泥社に加入しており、オブジェ焼の作品が残っている。また、十二代三輪休雪/龍気生もかつては走泥社のメンバーであった。確かに、三輪家代々ながらの茶陶を作成していたが、彼の本領はまさしくオブジェ焼なのであろう。
戦後の復興から新しい陶芸を追求して誕生した走泥社は50年の活動をもって終止符を打っている。もはや「前衛的」という冠詞をつけなくとも、多くの陶芸家が自由な造形で自由な表現の作品を作るようになり、走泥社の役割自体が普通のものとなっていたのである。
\画像を送って待つだけ!LINEで無料査定を希望の方はこちら/
URL:https://kotto-kotaro.com/line/
\メールで無料査定を希望の方はこちら/
URL:https://kotto-kotaro.com/assessment/
WEBからメール、LINEで簡単査定! 24時間受付中!お気軽にどうぞ!
お問い合わせ・ご予約 店舗電話受付時間 9:30-18:00 0120-922-157
関連記事
買取実績
こたろうの買取品目一覧
絵画
掛軸
茶道具
陶器・磁器
中国骨董品
刀剣・日本刀・武具
工芸品
漆器
彫刻
木工品
西洋アンティーク・西洋陶器・西洋美術品
珊瑚
骨董品
古銭
書道具
切手
アンティーク家具
べっ甲
時計・貴金属・宝石
古書