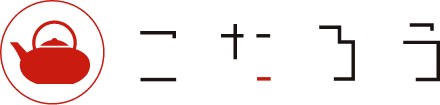油揚げのやきもの? 黄瀬戸/加藤唐九郎・魯山人/あぶら揚手・ぐい呑手・菊皿手

●唐九郎 襲撃さる
昭和期の名工であり奇才の加藤唐九郎は作陶だけでなく、本の執筆も行っていた。唐九郎は昭和八年、「黄瀬戸」という書籍を執筆し、発刊された。内容は黄瀬戸をはじめとする志野、織部や瀬戸黒について記してある。しかし、この書籍が唐九郎の出身地である瀬戸で大問題を起こした。この書籍で唐九郎は、加藤藤四郎景正について、実在の人物かどうかという疑問を提起するとともに、瀬戸焼の開祖ではないと論じたからである。加藤藤四郎景正は、鎌倉時代の陶工であり、近世・瀬戸焼の礎を作った人物であると、瀬戸では語り続けられている。事実。現在でも加藤姓の陶芸家のなかには、その末裔であることを「陶祖〇〇世」として陶歴等に記す者は多い。つまり、唐九郎は自分たち先祖の存在に疑問を呈したから、当時の瀬戸の陶工たちは怒り心頭に達し、さらに名古屋の新聞社が唐九郎の批判記事を掲載したことで、「唐九郎憎し」の機運は高まった。その結果、彼ら瀬戸の陶工たちは、唐九郎の「黄瀬戸」ほ梵書として集めて燃やした。また、唐九郎の工房に押し入ったり、夜間にはビール瓶で唐九郎を殴るという傷害事件にまで発展したそうである。

●黄瀬戸の発祥
瀬戸という名称のため、現在の愛知県瀬戸市近辺が発祥と思いきや、窯跡の発掘により現在では岐阜県美濃地方が発祥であるとされている。なぜ、瀬戸という名称がつけられてしまったかというと、鎌倉時代から室町時代までは瀬戸地方に陶器の窯が多くあり、瀬戸と美濃は一山隔てるだけの隣接地のため、同一地区として理解されていたという説がある。戦国時代になると「瀬戸山離散」と後に呼ばれる陶工の美濃地方への移動があったが、その後、江戸時代には美濃から瀬戸へと陶工が戻ることとなり、窯業地としての瀬戸が近世まで定着した。そのため昭和初期までは、美濃地方が発祥の美濃陶=黄瀬戸、織部、瀬戸黒、志野などでも、瀬戸地方で焼成され、瀬戸が発祥の陶器とみなされていたのである。したがって、黄瀬戸は江戸時代でも窯業地・瀬戸で焼成され続けており、名称自体はなんの違和感のないものであった。
その後、昭和初期に荒川豊蔵、魯山人などの美濃地方窯跡発掘によって、掘り出された陶片から美濃地方が発祥と解明されつつあった。これに前後して、先の唐九郎「黄瀬戸」が発刊されてしまったから、瀬戸の陶工たちは唐九郎の説をいかんとも受け入れなかったのである。
●黄瀬戸とは
黄瀬戸とは文字どおり、黄色い釉薬の陶器である。基本的には原始的な木の灰と陶土または長石の二種混合と呼ばれる釉薬が使われたとみられ、還元焼成で焼かれると青い青磁に、酸化焼成で焼かれると黄色い黄釉となり、後者が正に黄瀬戸である。古代中国の陶磁器でもこの二種類の傾向は数多く認められている。
そのため黄瀬戸は還元焼成に失敗した青磁が始まりあると推察されることもあるようであるが、特に桃山時代の茶道の発展において、陶器の多様性が追求されたことが、明るい色合いの陶器が珍重されるようになり、黄瀬戸が好まれるようになったのかもしれない。それは白い陶器として日本で初めて焼かれた志野や鮮やかな緑色の織部などが生まれていった流れと重なる。

●黄瀬戸の味わい
黄瀬戸には釉薬の表情の違いから大きく3つに分けられる。一つ目は、ぐい呑手と呼ばれる光沢のあるタイプ。二つ目は、あぶら揚手/あやめ手と呼ばれる半光沢のタイプ。三つ目は、ぐい呑手より釉薬が厚くかかり、より光沢のある菊皿手というもので、大量生産されたものがこれに該当する。コレクターに一番人気のあるものが、あぶら揚手であり、古陶でも珍重されているものである。確かにこのあぶら揚手は、再現も難しい。おそらくぐい呑手に至る前の釉薬が溶け切らない前の状態に近いものがあぶら揚手になっているものと思われるが、現代の陶芸家でも、このあぶら揚手の再現に苦労しており、満足のいく焼き上がりは少ないという。唐九郎はその再現のために木灰をウバメ樫の灰に絞り込み、再現を試みた。魯山人は瀬戸の陶芸家・加藤作助から釉薬を分けてもらっていたようだが、この黄瀬戸釉では満足のいくあぶら揚手とはならず、むしろ瀬戸や美濃の陶土をあえて用いず、信楽の粗めの陶土を使用して釉薬の表情をあぶら揚手に近づけるという工夫をした。さらに匣/さやに作品を入れるとともに、泥を底に敷き、そこから蒸発する水分で釉薬の肌合いを調整した。
その他の陶芸家でも、あぶら揚手の黄瀬戸に挑む陶芸家にとっては独自の工夫が必要な難しい陶器であることは、今日でも変わりがない。
\画像を送って待つだけ!LINEで無料査定を希望の方はこちら/
URL:https://kotto-kotaro.com/line/
\メールで無料査定を希望の方はこちら/
URL:https://kotto-kotaro.com/assessment/
WEBからメール、LINEで簡単査定! 24時間受付中!お気軽にどうぞ!
お問い合わせ・ご予約 店舗電話受付時間 9:30-18:00 0120-922-157
関連記事
買取実績
こたろうの買取品目一覧
絵画
掛軸
茶道具
陶器・磁器
中国骨董品
刀剣・日本刀・武具
工芸品
漆器
彫刻
木工品
西洋アンティーク・西洋陶器・西洋美術品
珊瑚
骨董品
古銭
書道具
切手
アンティーク家具
べっ甲
時計・貴金属・宝石
古書